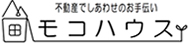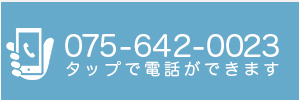京都市伏見区の不動産「モコハウス株式会社」です
コラム
プロが教える不動産の豆知識

トップページ > コラム
プロが教える不動産の豆知識
Column
【2025年度版】京都で住むなら賃貸? 購入? 最新動向から徹底比較!

京都の不動産 モコハウスです。
「賃貸と購入、結局どちらがお得なの?」
この問いは、多くの方が抱える疑問ですよね。特に2025年の日本では、物価上昇や金利の動き、そして多様化するライフスタイルといった要素が絡み合い、その判断はますます複雑になっています。
今回は、信頼できる最新の経済データや税制改正点を基に、京都での住宅選びにおける賃貸と購入、それぞれのメリット・デメリットを改めて徹底的に比較検証していきます。
2025年の経済・金融環境予測:住宅選択にどう影響するか
まず、2025年の日本経済が住宅選択に与える影響を、公表されているデータに基づいて見ていきましょう。
物価と賃金の動向
物価上昇は当面続く見通しです。
日本銀行が公表した『経済・物価情勢の展望(2024年4月)』によると、消費者物価指数(CPI、除く生鮮食品)は、2024年度に+2.8%、2025年度には+1.9%の上昇が見込まれています。エネルギー価格の高止まりなどを背景に、企業はコスト増を価格転嫁する動きが続くと考えられます。
一方で、賃金にも上昇の動きが見られます。2024年の春闘では高い賃上げ率が実現しましたが、三菱総合研究所などの調査機関は、2025年の春闘でも高水準の賃上げが続くと予測しています。これにより、物価上昇に賃金の上昇が追いつき、実質賃金が緩やかに改善していく可能性が示されています。
この状況は、物価高が家計を圧迫する一方、賃金上昇がそれを補うという構図です。住宅選びにおいては、この収支バランスを慎重に見極めることが、これまで以上に重要になるでしょう。
金融政策と金利動向
日本銀行は2024年3月にマイナス金利政策を解除し、政策金利を引き上げました。
これを受け、住宅ローン金利も変動の局面を迎えています。
- 変動金利: すぐに大幅な上昇は見られていませんが、将来的な金利上昇を見越した動きも出てきています。
- 固定金利: 長期金利(新発10年国債利回り)の上昇を受け、住宅ローンの固定金利は既に上昇傾向にあります。
金利の上昇は返済額の増加につながるため、住宅購入のハードルを上げる要因となります。
ただし、歴史的に見れば依然として低金利水準にあるという見方もあり、資金計画を慎重に立てることが求められます。
賃貸のメリット・デメリットと2025年の市場動向
賃貸の主なメリット
- 流動性の高さ: 転勤や家族構成の変化など、ライフステージの変化に柔軟に対応できます。
- 初期費用の抑制: 購入に比べ初期費用が少なく、貯蓄を他の用途に回せます。
- 維持管理コストの負担なし: 固定資産税や大規模修繕の費用はオーナー負担です。
- 災害リスクの分散: 建物の損害に対する直接的な経済的負担を負いません。
賃貸の主なデメリット
- 資産にならない: 家賃は消費であり、資産としては残りません。
- カスタマイズの制限: 原状回復義務があり、リフォームなどは基本的にできません。
- 家賃上昇リスク: 景気や周辺環境の変化で、更新時に家賃が上がる可能性があります。
- 更新料・再契約コスト: 数年ごとに更新料がかかり、引っ越せば再度初期費用が必要です。
2025年の賃貸市場動向
全国的に家賃は上昇傾向にあり、特に都市部でその動きが顕著です。
京都府の平均家賃も上昇基調が続いています。京都市内では、中京区や東山区といった人気エリアの築浅ファミリー向け物件(60㎡前後)を中心に、平均家賃が10万円を超える水準となっています。都心部への人口流入は続いており、需要は旺盛です。
賃貸契約の初期費用は、一般的に家賃の4.5ヶ月~6ヶ月分が目安とされています。
購入のメリット・デメリットと2025年の市場動向
購入の主なメリット
- 資産形成とインフレへの備え: 住宅はインフレ下で価値を保ちやすい資産とされます。ローン完済後は住居費負担が大幅に減り、経済的な安定につながります。ただし、資産価値は立地や物件の状態で大きく変動するため、将来の価値を保証するものではありません。
- 居住の安定と自由なカスタマイズ: 転居の心配がなく、自分好みの空間を自由に作れます。
- 住宅ローン控除による税制優遇: 条件を満たせば、所得税などが還付される大きなメリットがあります(後述)。
- 団体信用生命保険による保障: ローン契約者に万一のことがあっても、保険でローンが完済され家族に負債が残りません。
購入の主なデメリット
- 多額の初期費用と維持コスト: 物件価格の7%~10%の諸費用に加え、固定資産税、修繕費、管理費(マンションの場合)が毎年かかります。
- 流動性の低さ: 住み替えが必要になっても、すぐに売却できるとは限りません。
- 金利変動リスク: 変動金利では、将来金利が上昇すると返済額が増えるリスクがあります。
- 資産価値下落リスク: 人口減少や建物の老朽化、周辺環境の変化などにより資産価値が下落する可能性があります。
2025年の購入市場動向
不動産価格は高止まりの傾向が見られます。
- 新築マンション: 建築コストの高騰が続いており、新築価格は高水準を維持しています。
- 中古マンション: 近畿圏不動産流通機構(近畿レインズ)のデータによると、京都市の中古マンション成約価格は2020年以降、一時的な横ばい期間を挟みつつも上昇基調が続いています。24年に一旦調整局面を見せたが、中長期では引き続き上昇基調です。
- 都市部と地方の二極化: 京都市中心部など需要の堅いエリアでは価格が維持されやすい一方、郊外や地方では人口減少による価格下落のリスクも考慮すべきです。
【重要】住宅ローン控除の最新情報(2025年入居の注意点)
住宅ローン控除は大きなメリットですが、制度が年々変更されており、特に2025年は注意が必要です。
- 控除の基本: 控除額は年末ローン残高の0.7%で、原則13年間(中古は10年間)続きます。
- 子育て世帯等への優遇: 子育て世帯・若者夫婦世帯が認定住宅などを取得する場合の借入限度額上乗せ措置は、2025年末の入居まで延長されました。
- 【最重要】省エネ基準の必須化: 2024年1月以降に入居する場合、省エネ基準を満たさない「その他の住宅」は、原則として住宅ローン控除の対象外となります。
- より正確に言うと、「その他の住宅」に対する控除制度は、2023年末までに建築確認を受けた住宅が2025年中に入居する場合を最後に終了します。
- 2025年以降に入居する場合、省エネ基準を満たしていることが控除を受けるための必須条件となります。
- 新築と中古の違い: 中古住宅は控除期間が10年、借入限度額も新築より低く設定されているなど違いがあるため、注意が必要です。
- 中古住宅の「その他」区分は現行も存続しています(省エネ要件は不要)
これからの物件選びでは、「省エネ性能」が税制優遇を受けられるかどうかを左右する極めて重要な要素になります。
ライフスタイルとリスク許容度に応じた選択肢
結局のところ、どちらが最適かは個々の状況によります。
賃貸が有利なケース
- 転勤や移住の可能性があり、身軽でいたい方。
- 初期費用を抑え、自己資金を他の投資や経験に使いたい方。
- 不動産の維持管理や価値下落のリスクを負いたくない方。
- 将来の金利上昇に不安を感じる方。
購入が有利なケース
- 長期的な視点で資産を形成し、インフレから資産価値を守りたいと考える方。
- 「終の棲家」として、自由にリフォームなどを楽しみたい方。
- 子育て世帯・若者夫婦世帯で、省エネ性能の高い住宅を購入し、住宅ローン控除を最大限活用できる方。
- 将来の金利上昇にも耐えうる、安定した収入基盤がある方。
- 資産価値が維持されやすい傾向のある、都市部の優良物件を検討している方。
まとめ:最適な選択はあなた次第

2025年の住宅選択は、過去の常識にとらわれず、個々の状況に合わせた冷静な判断が求められます。
物価や金利の上昇は住宅購入のハードルを上げますが、賃金上昇の期待や、条件を満たす購入者への税制優遇もあります。
一方、賃貸も家賃の上昇傾向から「とにかく安い」とは言えなくなっています。
最終的な「最適解」は、ご自身のライフプラン、経済状況、そしてリスクをどこまで許容できるかによって決まります。
モコハウスでは、お客様一人ひとりのライフプランに合わせた最適な住宅選択を、客観的なデータに基づいてサポートいたします。
カフェで一休みする感覚で、ぜひお気軽にご相談ください!
経験豊富な宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー、住宅ローンアドバイザーの資格を持つスタッフが、あなたの幸せのお手伝いをさせていただきます。看板犬もお待ちしております!
関連リンク
過去の記事一覧
 2026年「金利ある世界」の住宅ローン選び! 変動金利のリスクとフラット35拡充の活用術
2026年「金利ある世界」の住宅ローン選び! 変動金利のリスクとフラット35拡充の活用術 マイホーム購入の新常識? 「残価設定型住宅ローン」を徹底解説!
マイホーム購入の新常識? 「残価設定型住宅ローン」を徹底解説! マンション購入後にかかる「住宅ローン以外」のお金とは? 維持費・税金の目安を徹底解説
マンション購入後にかかる「住宅ローン以外」のお金とは? 維持費・税金の目安を徹底解説 住宅ローン減税の期間延長、面積要件も緩和へ!
住宅ローン減税の期間延長、面積要件も緩和へ! 伏見区深草の地域情報! 「ふかくさ100円商店街」で防災意識を高めよう
伏見区深草の地域情報! 「ふかくさ100円商店街」で防災意識を高めよう 伏見の秋は日本酒日和! 伏見の清酒まつりで地元満喫
伏見の秋は日本酒日和! 伏見の清酒まつりで地元満喫 住宅ローン金利の行方! 高市新首相の発言から読み解く日銀の金融政策と市場への影響
住宅ローン金利の行方! 高市新首相の発言から読み解く日銀の金融政策と市場への影響 空き家法改正で固定資産税が最大6倍に! 知らないと怖い「管理不全」のリスク
空き家法改正で固定資産税が最大6倍に! 知らないと怖い「管理不全」のリスク 御香宮神社「神幸祭」の見どころ徹底解説! 徳川ゆかりの格式高い大祭
御香宮神社「神幸祭」の見どころ徹底解説! 徳川ゆかりの格式高い大祭 伏見酒回廊で蔵巡り! 11蔵をハシゴする楽しみ方とおすすめモデルコース
伏見酒回廊で蔵巡り! 11蔵をハシゴする楽しみ方とおすすめモデルコース 建築会社倒産で2,000万円が! 夢のマイホームを絶望に変えないための完全防衛マニュアル
建築会社倒産で2,000万円が! 夢のマイホームを絶望に変えないための完全防衛マニュアル 【2025年9月最新】住宅ローン金利上昇は本番へ! 変動と固定どっちを選ぶ? 専門家が徹底解説
【2025年9月最新】住宅ローン金利上昇は本番へ! 変動と固定どっちを選ぶ? 専門家が徹底解説 伏見の夏の風物詩! 伏見稲荷大社「宵宮祭・本宮祭」の魅力と歴史
伏見の夏の風物詩! 伏見稲荷大社「宵宮祭・本宮祭」の魅力と歴史 【2025年度版】京都で住むなら賃貸? 購入? 最新動向から徹底比較!
【2025年度版】京都で住むなら賃貸? 購入? 最新動向から徹底比較! 【2025年6月最新版】変動か? 固定か? 住宅ローン金利「二極化」時代の賢い選択術
【2025年6月最新版】変動か? 固定か? 住宅ローン金利「二極化」時代の賢い選択術 京都市伏見区のお店探訪 – 竹田駅すぐ!「キムキムチキン」で本場韓国の味と雰囲気を満喫!
京都市伏見区のお店探訪 – 竹田駅すぐ!「キムキムチキン」で本場韓国の味と雰囲気を満喫! 京都伏見で楽しむ、春爛漫の桜巡り2025🌸おすすめスポットと開花情報
京都伏見で楽しむ、春爛漫の桜巡り2025🌸おすすめスポットと開花情報 【京都伏見区】城南宮の梅と椿が織りなす幻想的な世界:アクセス・歴史・見どころ紹介
【京都伏見区】城南宮の梅と椿が織りなす幻想的な世界:アクセス・歴史・見どころ紹介 京都市の冬に気をつけたい水道管凍結対策
京都市の冬に気をつけたい水道管凍結対策 京都伏見太閤バル2025で食べて飲んで楽しもう!
京都伏見太閤バル2025で食べて飲んで楽しもう! 商売繁盛を願う! 伏見区の金札宮 えびす詣りとは?
商売繁盛を願う! 伏見区の金札宮 えびす詣りとは? 2024年12月の住宅ローン金利動向レポート
2024年12月の住宅ローン金利動向レポート 子育て世代を支援 京都安心すまい応援金を徹底解説
子育て世代を支援 京都安心すまい応援金を徹底解説 住宅ローン金利の種類を理解しよう! 基準金利、優遇金利、適用金利とは?
住宅ローン金利の種類を理解しよう! 基準金利、優遇金利、適用金利とは? 京都市伏見区の紅葉名所 穴場スポットから定番までご紹介!
京都市伏見区の紅葉名所 穴場スポットから定番までご紹介! 【11/23開催】深草で100円商店街?! 秋の深草を満喫するイベント盛りだくさん!
【11/23開催】深草で100円商店街?! 秋の深草を満喫するイベント盛りだくさん! 京都市伏見区で土地活用をお考えの方へ! 最適な活用法を見つけよう!
京都市伏見区で土地活用をお考えの方へ! 最適な活用法を見つけよう! 住宅ローン返済 元利均等と元金均等の違い どっちがお得?【金利上昇リスクを詳しく解説】
住宅ローン返済 元利均等と元金均等の違い どっちがお得?【金利上昇リスクを詳しく解説】 外壁塗装のタイミングと費用相場
外壁塗装のタイミングと費用相場 自宅を売却するまでにかかる期間は? 媒介契約と買取保証制度、査定のポイントについても解説
自宅を売却するまでにかかる期間は? 媒介契約と買取保証制度、査定のポイントについても解説 リフォームで理想の住まいを実現! 失敗しないための基礎知識と補助金活用術
リフォームで理想の住まいを実現! 失敗しないための基礎知識と補助金活用術 京都市伏見区 與杼神社 秋季大祭:歴史と見どころを詳しく解説!
京都市伏見区 與杼神社 秋季大祭:歴史と見どころを詳しく解説! 相続税対策の基礎知識! 生前贈与の7年ルールとは?【改正点も解説】
相続税対策の基礎知識! 生前贈与の7年ルールとは?【改正点も解説】 京都伏見で初開催! 「パンまみれフェス」で食欲の秋を満喫しよう!
京都伏見で初開催! 「パンまみれフェス」で食欲の秋を満喫しよう! 相続した不動産、放置していませんか? 相続登記の義務化で知っておくべきこと
相続した不動産、放置していませんか? 相続登記の義務化で知っておくべきこと 今週末は伏見の酒蔵へGO! 秋の蔵開きイベント盛りだくさん!
今週末は伏見の酒蔵へGO! 秋の蔵開きイベント盛りだくさん! 初めての不動産購入でも安心! 基礎知識をわかりやすく解説
初めての不動産購入でも安心! 基礎知識をわかりやすく解説 平安遷都の日 とは? 京都・伏見区の賃貸事情と不動産投資の魅力
平安遷都の日 とは? 京都・伏見区の賃貸事情と不動産投資の魅力 老朽化した住宅を建て替える? 知っておきたい基礎知識
老朽化した住宅を建て替える? 知っておきたい基礎知識 不動産投資のリスクと対策
不動産投資のリスクと対策 初心者にもおすすめ! マンション投資で安定収入を目指そう!
初心者にもおすすめ! マンション投資で安定収入を目指そう! 伏見区の空き家問題、相続・活用のご相談はモコハウスへ
伏見区の空き家問題、相続・活用のご相談はモコハウスへ 貯蓄の日 – 未来への安心を育む「貯蓄」のススメ
貯蓄の日 – 未来への安心を育む「貯蓄」のススメ なぜ不動産屋さんは水曜休みが多いの?
なぜ不動産屋さんは水曜休みが多いの? 住宅ローンの金利動向について
住宅ローンの金利動向について 健康的な暮らしと住まい選び
健康的な暮らしと住まい選び 迫力満点! 三栖神社の炬火祭
迫力満点! 三栖神社の炬火祭 御香宮神社の神幸祭
御香宮神社の神幸祭 お部屋探しでやって欲しい重要ポイント
お部屋探しでやって欲しい重要ポイント 不動産売却の基礎知識
不動産売却の基礎知識